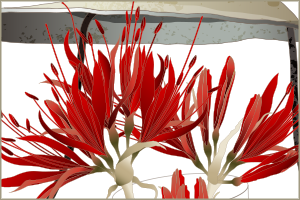
彼岸花
秋のお彼岸に咲く花で別名曼珠沙華
彼岸に咲くので死者を連想させやすく、球根にある毒も相まってネガティブな印象を持たれます。
曼珠沙華という別名はサンスクリット語の「天界に咲く花」なんですけどね。
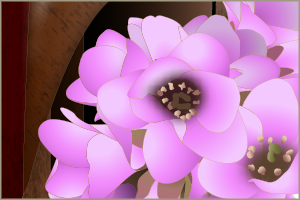
ヒマラヤユキノシタ
ヒマラヤ山脈周辺が原産の植物です、
耐寒性も乾燥耐性もあり、過酷な状況下でも生き延びるたくましさが特徴。
なので花言葉は 忍耐 秘めた感情 だそうです。納得しますね。

姫檜扇水仙
明治の中頃から栽培されるようになった花ですが、現在では野生化しています。

ヒヨドリジョウゴ
ヒヨドリが群がって食べる様子が酔っ払いのようだと言うことでこの名前がつきました。
赤い実が実に美しい姿なのに、ひどいですよね。

ホオズキ
八岐大蛇の目にも例えられた実です。
鬼灯とも書きますが、お盆の提灯に見立てたホオズキの色が怪しげに見えるからとか。
何か、あの世とかファンタジーに縁がある植物みたいですね。

鳳仙花
鳳の文字が入っていますよね。鳳凰に見立てた花だからだそうです。
別名を爪紅とも言い、平安時代から鳳仙花を潰して爪に塗る化粧法がありました。

ホヤハート
多肉植物です。
見てご覧の通りハートの形をしていてすごくキュートなので描いてみました。

百日草
初夏から晩秋まで長期間咲くので百日草の名前が付きました。
ウラシマソウという別名もあって、これは花期が長いため浦島太郎にちなんだそうです。

一輪草
春先の花を付け、その後は地下で過ごすスプリング・エフェメラル。
花の裏が紅色になることから裏紅一花とも呼ばれています。

犬蓼
雑草ですね。道端や畑などに普通に生えているのを見かけます。
子どもの頃おままごとでこれをお赤飯に見立てていました。
アカマンマの別名があります。

アイリス
ギリシャ神話の女神、イリスに由来します。
イリスは虹の女神で、この花が七色になることからアイリスという名になりました。

ジャスミン
インドからアラビアにかけての熱帯・亜熱帯アジア原産の花です。
強い芳香が特徴ですね。
ジャスミンはペルシャ語で神の贈り物を意味するそうです。

沈丁花
早春に強く香って存在を示してくれる花。
室町時代に渡来した日本三大香木(クチナシ・キンモクセイ)の一つです。

ジュリエット・ローズ
まるで牡丹のようですが薔薇です。
最も高価な薔薇だと言われていますね。
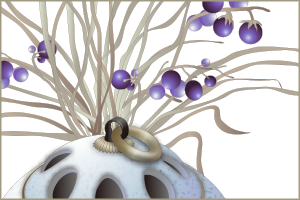
蛇の髭
日本各地に自生する多年草です。
秋にコバルトブルーの実をつけ3月頃まで残るので冬枯れの中、目立ちます。
ふと思ったのですが、蛇って髭ありましたっけ?

寒緋桜
旧暦のお正月あたりから緋紅色の花を咲かせる桜です。

唐種招霊
唐から渡来し霊を招くという意味で付いた名前らしいです。
この花が招霊(オキタマ)とどういう関係があるのかはわかりませんでした。
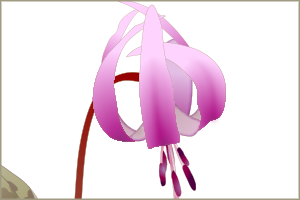
カタクリ
早春の落葉樹林に咲く可憐な花。春の妖精とも言われています。

苔竜胆
草の丈が低いので見落とされがちな小さい花です。
でも花の色は鮮やかな青で、これは目立つかもしれません。

クサギ
漢字で書くと臭木で、とてもとても臭い花だと言います。
でも見た目が面白かったので描いてみました。