
レウイシア
北アメリカのロッキー山脈~カリフォルニアの山地の岩場などに自生している高山植物
なんといっても見た目の華やかさが気に入りました。
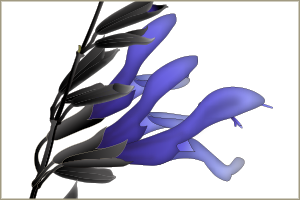
メドーセージ
濃い青紫の花と、黒い顎が印象的な南米原産の花です。
サルビア・ガラニチカという名もあり、サルビアの仲間でもありますね。
渋いけど目を引く色の花です。

紅葉
紅葉には二つの読み方があって、読み方により意味が変わります。
紅葉(もみじ)は楓の仲間のこと。紅葉(こうよう)は秋の木々が色を変える現象
ここは楓の仲間のもみじです。

紅葉葵
紅葉葵は和名で葉の形が「もみじ」のようなのでそう呼ばれています。
別名 紅蜀葵(こうしょくき)

モンステラ
独特の見た目でインテリア性の高い植物ですよね。
別名に蓬莱蕉というのがあって、蓬莱山に生えているような植物だから、だそうです。
蓬莱山というのは伝説上の神山を言います。

紫式部
秋の初めに雑木林などで見かける、赤紫の実をつける植物です。
名の由来ですが、紫色に熟す重なり合った実を京では紫重実(むらさきしきみ)というので
それでは平安時代の女流作家、紫式部にしましょうとなったらしいです。

射干玉(ぬばたま)
檜扇の実を「ぬばたま」いいます。
黒くつややかで、数ある実の中でも美形のトップを飾るのではないでしょうか。
この実は和菓子にもなっていたりします。

苧環
機織りの際に使う、麻糸を巻き付けた苧環に形が似ていることからこの名が付きました。
しずやしず しずのをだまきくり返し 昔を今になすよしもがな
静御前が頼朝の前で舞い歌ったことで有名ですよね。

おかめ桜
寒緋桜とマメザクラの交配で生まれた品種で、早咲きで濃いピンクとい特徴を持っています。
この花のあまりの美しさに美人の代名詞だったおかめの名を与えたそうです。

沖縄スズメウリ
沖縄に自生している植物で、おもちゃみたいに可愛い実をつけます。
ですがこの実は有毒で食べられません。観賞用です。

万年青
観賞用として日本で改良された園芸種です。
常緑の万年青は長寿や永遠の繁栄といった大変おめでたい花言葉を持つので
床の間などに飾られるようになりました。

乙女椿
日本原産の八重咲きの椿です。
なかなか落下しないので、枝に残って茶色に変色したりして
桜とは正反対な性格の花だったりします。乙女なのに残念なことですね。

オキザリス・トリアングラリス
和名 紫の舞
花壇や鉢植え、グランドカバーとしても楽しめる植物です。

ポインセチア
クリスマスに引っ張りだこの花なので、クリスマスフラワーとも呼ばれています。
原産地のメキシコでは「聖夜」などを意味する「ノーチェ・ブエナ」といい
赤い色はキリストの血であるとかで誕生祭に使われるようになります。
そんなこんなでクリスマスの花になったようですよ。
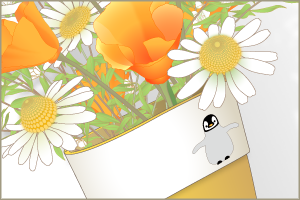
レインブーツ
長靴にいろんな花を放り込んでみたいと思いまして描いてみました。

レインボーローズ
実際は白い薔薇に色を塗って作ったものです。
色水を使った方法もあるようですが、この薔薇はどうみても塗った感じですね。

蝋梅
冬に咲く花です。
花びらの質感が蝋のようで、梅に似た花の形からこの名が付きました。

実葛
別名に美男葛というのがあります。
若い蔓から採れる粘液を男性が整髪料として使っていたためそう名が付いたとか。
実の色が美しいからという説もあるそうです。

山茱萸
秋に茱萸に似た実をつけます。山茱萸と書いてサンシュ(中国語の音読)
秋珊瑚とも呼ばれていて生食には不向きです。
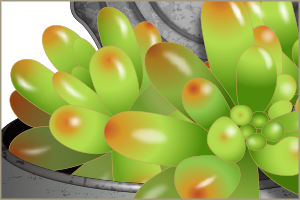
セダム
多肉植物です。このつやつやしたビジュアルが何とも言えません。観葉植物ですねぇ。